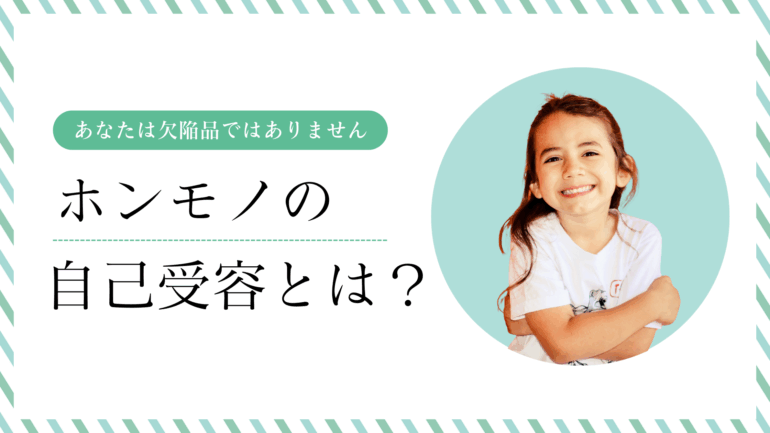こんにちは! 『変容のフェーズ診断Ⓡ』メイです。
ネットや本や動画で「自己受容しましょう」とここまで広く言われているのに、なぜ私たちは無意識のうちに「勝ち負け」や「評価」といった競争や比較の世界に身を置いているのでしょうか? もしかすると、「自己受容」という言葉の本来の意味が正しく伝わっていないのかもしれません。
ということで「本物の自己受容」について記事にしておきたいと思います。
自己受容=自分を褒める?!
「とりあえず自分を褒めてみよう」という方法は、気分を軽くする助けにはなります。 けれど、それを”自己受容”とイコールにしてしまうと、ちょっと違います。
なぜなら「褒める」という行為は、どうしても”評価の枠組み”に乗っかってしまうからです。 「できたから良い」「できなかったらダメ」という基準が残ったままでは、根本的には自己否定から抜け出せないことが多いんです。
例えば、「今日は早起きできた私、えらい!」と褒めたとしても、明日早起きできなかったら「やっぱりダメな私」に戻ってしまう。これは結局、単なる条件付きの自己肯定にすぎません。
本当の自己受容は、早起きできてもできなくても、そこにジャッジ(良い悪いの判断)を持ち込まない状態です。「今日は早く起きた」「今日は遅く起きた」という事実をただ事実として受け取れる。そんな評価を超えた視点を育てることなんです。
褒める代わりにできること
・事実を淡々と観察する:「今、こんなことを感じているな」
・感情に名前をつける:「あ、今焦りを感じているんだ」
・自分への優しい声かけ:「大丈夫、一歩ずつでいいよ」
丸ごと受け入れるのは一気にはできない
「ありのままを丸ごと受け入れましょう」 とても素敵な言葉ですが、いきなり全部を受け入れるのは現実的には難しいものです。
心の奥には、これまで抑えてきた怒り・悲しみ・嫉妬・孤独などが眠っています。 その感情を解放しないまま「全部OK」と言い聞かせようとすると、ザワザワするのは自然なことです。 むしろ「やっぱり受け入れられない」と落ち込んでしまい、また自己否定に戻ってしまうことすらあります。
段階的なアプローチの大切さ
まずは小さな部分から始めてみる。今日失敗してしまったこと、ちょっとした癖、人には言えない小さな感情。そういった「受け入れやすい部分」から少しずつ練習していく方が、結果的に確実に前に進めます。
また、感情は抑え込むのではなく、まずは「感じ切る」ことが大切です。悲しみなら悲しみを、怒りなら怒りを、安全な環境でしっかりと味わい尽くす。そうすることで初めて、その感情が自然と手放されていくのです。
受け入れられない自分も受け入れる
そして、「受け入れられない自分」がいることも、また受け入れる対象です。「まだ受け入れられない部分があってもいい」「今はまだここまでで十分」という余白を自分に与えることが、かえって受容への道を開いていきます。
*****
こうした過去の抑圧されたトラウマ的な感情の解放するセラピーとプログラムを提供しています。
経験上、セラピーで解放する方が断然早く、効果的です。感情が残っているかどうかをスケールで測りながら進めていくので、納得感を得ながら進めることができます。
ご興味がある方はプロフィールのHPからご相談くださいね。
他人目線のワナ
多くの人が「短所を直さないと」「人に迷惑をかけないように」と考えて、自分を改善しようとします。 一見もっともらしく聞こえますが、よくよく見ると”他人から否定されないため”という理由だったりします。
これだと、せっかくの努力も「自分のままではダメ」という刷り込みを強めてしまうんですね。
「良い人」症候群の落とし穴
特に日本では「和を乱さない」「空気を読む」ことが美徳とされがちです。でも、その結果として「本当の自分」を見失ってしまう人が少なくありません。
常に相手の顔色をうかがい、期待に応えようとし続けていると、「自分が何を本当に感じているのか」「自分は何を望んでいるのか」がわからなくなってしまいます。
内側からの動機を育てる
本当の成長は、他人のためではなく「自分がより良い人生を歩みたいから」「自分がより自由になりたいから」という内側からの動機によって起こります。
例えば、短気な性格を直したい時も「周りに迷惑をかけないため」ではなく、「自分がもっと穏やかに生きられたら楽しいだろうな」という視点から取り組む。そうすると、変化のプロセスそのものが自己受容を深める機会になっていくのです。
自己否定は自然に身についてしまう
思い返してみると、私たちは生まれてからずっと「ありのままではいけない」というメッセージを受け取ってきました。
「静かにしなさい!」
「いい子にしていなさい!」
「ちゃんとしなさい!」
もちろん、社会の中で必要な教育やしつけもたくさんあります。 ただ、その中に巧妙に紛れ込む形で「あなたは今のままではダメ」という声が潜んでいるんです。
だから、自己否定って特別なことではなく、とても自然に私たちの中に入る混んでしまうものなんですね。
無意識に内面化された「こうあるべき」
大人になった今も、私たちの頭の中には無数の「べき」が住み着いています。
・もっと頑張るべき
・完璧であるべき
・弱音を吐いてはいけない
・感情的になってはいけない
・みんなに好かれるべき
これらの多くは、子どもの頃に「愛されるため」「認められるため」に身につけた生存戦略でした。でも、大人になった今は、かえってその「べき」が自分を苦しめる足かせになっていることも多いのです。
完璧主義という名の自分攻撃
特に「完璧主義」は、一見すると向上心のように見えますが、実は「完璧でない自分は価値がない」という深い自己否定が隠れていることがあります。
完璧主義の人は、小さな失敗にも異常に落ち込み、成功しても「まだ足りない」と感じがちです。これは愛情や承認への飢えから生まれる、とても苦しいパターンです。
気づくだけで少し楽になれる
大切なのは、「これは自分の本質ではなく、長年刷り込まれた価値観なんだ」と気づけることです。 そう思えるだけでも、不思議と心が軽くなる瞬間があります。
ただ、この見分けは意外と難しいのです。 私も学んで初めて「これも自己否定なの?!」と驚いたことが何度もあります。
だからこそ、私はそのサポートをしているんです。
「観察者の視点」を育てる
自分の心の声を客観視する練習が役に立ちます。頭の中で批判的な声が聞こえてきた時、「あ、また『べき』の声が出てきたな」と気づけるようになる。
この「観察者の視点」は、瞑想やマインドフルネスの練習で育てることができます。毎日5分でも、自分の呼吸や感情を ただ観察する時間を作ってみると、徐々に心の声を客観視できるようになります。
子どもの頃の自分との対話
時には、その批判的な声がいつ頃から始まったのかを探ってみることも有効です。多くの場合、小さな子どもの頃の傷ついた体験と結びついています。
その時の自分に「よく頑張ったね」「あの時は仕方なかったよ」と優しく声をかけてあげる。すると、長年自分を苦しめてきた声が少しずつ和らいでいくことがあります。
本当の自己受容とは何か
では、本当の自己受容とは何でしょうか?
それは、自分の全てを「良い・悪い」で判断せず、ただ一般的にネガティブと思われる自分の要素ですら「そこにある」ものとして認識することです。
喜怒哀楽の感情も、得意不得意も、過去の失敗も成功も、全てが「自分という人間の一部」として存在している。その事実をありのままに受け取れる状態です。
受容は諦めではない
よく誤解されるのですが、自己受容は「諦め」や「現状維持」を意味しません。むしろ、ありのままの現状をしっかりと受け取れるからこそ、そこから本当に必要な変化を選択できるようになります。
自己否定のエネルギーで無理やり自分を変えようとするのではなく、自分への愛情と理解から「欠点もあるかもしれないけど、こんなふうになれたらいいな」という方向へ自然と向かっていく。これが健全な癒しと自己成長のプロセスです。
人との関係も変わる
自己受容が深まると、人との関係も大きく変わります。自分を受け入れられるようになると、他人のことも評価や判断なしに見られるようになる。
「どんな自分もOK=どんなあなたでもOK」になるのです。もちろん好き・嫌いは存在します。でも好き・嫌いすら自分に許しているので、自然に距離をとることができるのです。
そうして相手に無理な期待を押し付けることも、相手の評価に一喜一憂することもなくなります。
結果として、より深く、より自由な人間関係を築けるようになるのです。
実践的なステップ
1. 日記で感情を整理する
毎日寝る前に、その日感じたことを素直に書き出してみましょう。「こんなこと思ってはいけない」という検閲は一切なしです。怒り、悲しみ、嫉妬、不安… どんな感情も「あってもいいもの」として紙に記していきます。
2. セルフコンパッション(自分への思いやり)
失敗した時や落ち込んだ時、自分にどんな言葉をかけているでしょうか? 親友が同じ状況にいたら、どんなふうに声をかけますか?
自分にも同じような優しさを向けてみてください。「大丈夫だよ」「みんな失敗するよ」「一人じゃないよ」といった温かい言葉を、自分自身にかけてみる練習をしてみましょう。
3. ボディスキャン
体の感覚に意識を向ける練習も効果的です。頭のてっぺんから足の先まで、順番に意識を向けていく。どこか緊張している部分はないか、どこか痛みを感じている部分はないか。
体の声に耳を傾けることで、心の状態もより明確に把握できるようになります。
4. 境界線を引く練習
自分と他人の境界線を意識することも重要です。相手の問題と自分の問題をきちんと分ける。相手の機嫌は相手の責任で、自分がコントロールできることではない、ということを理解する。
NOと言える練習、自分の気持ちを素直に伝える練習も、自己受容を深める大切なステップです。
※私は意識で矯正しなくても自然に境界線が引けるようになる、自分軸を取り戻す【感情OS解放プログラム】を提供しています。
さいごに
自己受容は「とにかく褒めること」でも「いきなり全部を丸ごと受け入れること」でもありません。 本当に大切なのは、”ダメ出しの声”を見分けて、自分をそこから自由にしていくことだと思います。
このプロセスは一朝一夕には完成しません。時には後戻りしたり、立ち止まったりすることもあるでしょう。それでもいいのです。その歩みそのものが、すでに自己受容の実践なのですから。
一歩ずつ、あなたのペースで。
あなたはそのままで、すでに十分価値ある存在なのですから。
👉自分を「そのままで価値ある存在」と思えないとお悩みの方はお気軽にご相談ください。
📤初回特別価格1,000円/60分 お試しカウンセリングお申し込み
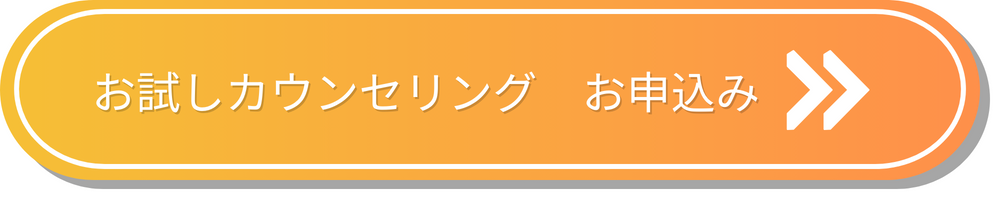
▼ 【公式LINE】にご登録いただいた方は、お試しカウンセリング60分のところ、30分無料延長特典プレゼント!
✨ただ今LINEお友だち募集中✨
お問い合わせ・ご予約にも
ご利用いただけます